
- 序章:教育が不動産市場を動かす時代へ
- 第1章:チェンマイの事例に見る教育主導型不動産開発
- 1-2. 賃貸市場への波及と投資家の動き
- 1-3. 学校計画のスケールが需要を広げる
- 1-4. 国際的な多様性とブランド力
- 1-5. 中国人家庭という強力な需要エンジン
- 1-6. 投資家にとっての実務的示唆
- 第2章:インターナショナルスクールが住宅需要を押し上げる仕組み
- 2-2. 在学期間の長期性が需要を固定化する
- 2-3. 親世帯と投資家の需要が重なり合う
- 2-4. 中国人家庭という強力な需要の担い手
- 2-5. 学校側のインセンティブが需要を後押し
- 2-6. 寄宿舎の導入で広がる需要の地理的範囲
- 2-7. アメニティ開発が生む“第二の価値波”
- 2-8. 賃料形成の実務
- 2-9. 価格安定のメカニズムを総括
- 第3章:地方都市別の動向比較
- 第4章:デベロッパー戦略の進化
- 第5章:マクロ経済と政策的背景
- 第6章:将来展望 ― 教育ハブとしてのタイ
- 結論:インターナショナルスクールはタイ不動産の「金鉱脈」
序章:教育が不動産市場を動かす時代へ
「教育が都市を変える」という言葉があります。近年のタイ不動産市場では、このフレーズが単なる比喩ではなく、実際の市場動向として顕著に表れています。
特に インターナショナルスクールの存在が住宅需要を直接押し上げる という現象は、首都バンコクだけでなくチェンマイやプーケット、チョンブリなどの地方主要都市でも観測されており、不動産投資家・デベロッパー双方から強い注目を集めています。
2025年9月現在、このトレンドは単なる一過性ではなく、タイ経済・社会構造の大きな変化を反映する長期的な潮流だと考えられています。本記事では、最新事例やデータをもとに、この「教育主導型開発モデル」の実態と今後の可能性を徹底的に掘り下げていきます。
第1章:チェンマイの事例に見る教育主導型不動産開発
1-1. ド1-1. ドイサケットで起きた“教育プレミアム”の顕在化
タイ北部の文化都市チェンマイでは、いま新しい潮流が生まれています。特に注目すべきは、上場デベロッパーのオーンシリン・ホールディングが取り組む教育主導型の開発です。というのも、同社が本社近隣に着手したミルヒル・インターナショナルスクール・タイランドの建設が、周辺住宅需要を劇的に押し上げているからです。
さらに、価格の推移を見ればその効果は明らかです。2024年半ばから同社は住宅価格を1回あたり10万〜30万バーツずつ、合計3回引き上げました。しかしながら、それでも販売スピードは落ちず、2025年5月の着工後も好調を維持しています。したがって、学校という教育インフラが、住宅価格に“教育プレミアム”を付加しているといえるのです。
1-2. 賃貸市場への波及と投資家の動き
一方で、住宅価格だけでなく賃料市場にも変化が表れています。例えば、3ベッドルーム・2バスルームで価格300万バーツの戸建てでは、リフォーム後に賃料が月額18,000バーツから29,000バーツへと上昇しました。この背景には、子どもを入学させたい親世帯の強いニーズがあるためです。
加えて、以前は売却物件として市場に出ていた住宅が、学校建設をきっかけに賃貸物件へ転換しています。結果として、親世帯にとっては住むための選択肢が広がり、同時に投資家にとっては安定した賃貸需要が保証される市場へと進化しているのです。
1-3. 学校計画のスケールが需要を広げる
では、なぜここまで住宅市場への影響が大きいのでしょうか。理由の一つは、学校計画のスケールにあります。ミルヒルは英国式カリキュラムを採用し、2025年の開校時点でナーサリーからYear 6までを受け入れます。さらに、2026年にYear 9、2027年にYear 13、2028年には寄宿舎まで拡張予定です。
このように段階的に拡張することで、通学期間は最長16年にも及びます。したがって、保護者は長期的に近隣住宅を求めざるを得ず、結果として周辺の不動産市場に持続的な需要が生まれるのです。
1-4. 国際的な多様性とブランド力
また、入学申請の国籍構成も注目に値します。現在100件の申請のうち、半分はタイ人家庭ですが、残りの半分は外国人で、その中でも25%は中国人、10%は英国人です。ただし、学校側は国際的な多様性を保つために、タイ人を除き国籍ごとに25%の上限を設けています。
このような方針は、一見すると需要を抑えるように見えます。しかし、実際には国際的ブランド価値を高める効果を持ち、結果としてより幅広い家庭からの関心を呼び込む要因となるのです。
1-5. 中国人家庭という強力な需要エンジン
さらに重要なのは、中国人家庭からの需要が非常に強いことです。なぜなら、中国国内ではインターナショナルスクールに対する規制が強化されており、子どもに質の高い教育を受けさせたい家庭が海外へ目を向けているからです。
加えて、授業料の差も大きな理由です。中国国内のインターナショナルスクールは年間100〜200万バーツに達することもありますが、タイでは40〜60万バーツに収まります。したがって、コスト面での魅力が中国人家庭の購買意欲を強力に後押ししているのです。
1-6. 投資家にとっての実務的示唆
このような環境下では、投資家も明確な戦略を立てやすくなります。例えば、家具や設備の質を引き上げることで賃料をさらに増額でき、利回り改善が期待できます。また、賃貸契約を学期サイクルに合わせることで空室リスクを最小化できます。
つまり、教育インフラに付随する住宅市場は、親世帯と投資家双方にとって**「需要が長期にわたり安定する投資機会」**を提供しているのです。
第2章:インターナショナルスクールが住宅需要を押し上げる仕組み
2-1. 通学時間が不動産価値を高める仕組み
まず注目すべきは、通学時間の削減が住宅価格に直結するという点です。というのも、親にとって子どもの送り迎えは日常的な負担であり、時間的コストやストレスは非常に大きいからです。したがって、学校の近くに住むことは、単に利便性を高めるだけでなく、家庭全体の生活の質を向上させる意味を持ちます。
さらに、通学時間が短ければ短いほど、子どもはより多くの睡眠時間や学習時間を確保できます。そのため、教育成果の向上にもつながりやすいと考えられます。このように、**「通学時間の短縮=教育成果と生活満足度の向上」**という認識が浸透することで、住宅価格や賃料に教育プレミアムが付与されるのです。
2-2. 在学期間の長期性が需要を固定化する
一方で、需要をさらに強固なものにしているのは、在学期間の長期性です。インターナショナルスクールはナーサリーから高校卒業(Year 13)まで在籍できるため、最長で16年間も同じ学校に通うことが可能です。
この長さは、住宅市場にとって非常に重要です。なぜなら、親世帯は子どもが卒業するまで転居を避ける傾向が強いため、居住需要が固定化されるからです。したがって、学校が存在するエリアでは、短期的な景気変動に左右されにくい安定した需要が形成されます。
さらに、子どもが卒業した後も、その住宅は次の学齢期の家庭に売却あるいは賃貸されるケースが多く見られます。つまり、需要が循環する市場構造が自然に生まれるのです。
2-3. 親世帯と投資家の需要が重なり合う
また、教育近接住宅市場の特徴は、親世帯の自用需要と投資家の投資需要が同一エリアで重なり合う点にあります。これは通常の不動産市場ではあまり見られない現象です。
具体的には、親世帯は「子どもの教育のために学校近くに住みたい」と考え、住宅を購入または賃借します。一方で投資家は、「教育需要があるから空室リスクが低く、利回りが安定する」と判断し、物件を購入して貸し出します。
したがって、売買市場と賃貸市場の両方が同時に活性化し、結果として住宅価格は上昇しやすく、賃料も下がりにくい状況が生まれます。これはまさに、教育需要がもたらす市場の二重構造といえるでしょう。
2-4. 中国人家庭という強力な需要の担い手
さらに重要な要素として、中国人家庭からの強い需要が挙げられます。なぜなら、中国政府が義務教育段階での外国カリキュラム使用を規制しているため、子どもの教育のために海外を選ぶ家庭が急増しているからです。
加えて、中国国内のインターナショナルスクールは学費が高騰しており、北京では年間100〜200万バーツに達する場合もあります。これに対し、タイの授業料は年間40〜60万バーツに抑えられるため、コスト競争力の差が極めて大きいのです。
その結果、特にチェンマイやプーケットでは、中国人家庭が不動産需要の主要なドライバーとなっています。つまり、教育需要が国境を越えて波及し、タイ不動産市場を押し上げているのです。
2-5. 学校側のインセンティブが需要を後押し
さらに、デベロッパーや学校側が提供するインセンティブも見逃せません。例えば、オーンシリンは自社の住宅購入者に授業料15%割引を提供しています。また、プーケットのSkyLuke Propertyはヴィラ購入者に対し、ルアムルディー・インターナショナルスクールの授業料50%割引を実施しました。
このように教育費の負担を軽減する特典は、保護者にとって非常に大きな魅力となります。なぜなら、授業料は毎年必ず発生する固定費であり、その削減効果は実感しやすいからです。したがって、この種のインセンティブは「住宅購入を今決断する理由」として強力に作用するのです。
2-6. 寄宿舎の導入で広がる需要の地理的範囲
さらに将来的には、寄宿舎の導入が市場に新しい波をもたらすでしょう。例えば、ミルヒルは2028年に寄宿舎を整備する予定です。これにより、遠隔地や海外からの生徒も受け入れやすくなり、地域を越えた需要が発生します。
ただし、寄宿舎が導入されても、親が子どもの近くに住みたいと考えるケースは依然として多いです。したがって、寄宿舎は需要を奪うのではなく、むしろ市場全体を拡張する役割を果たすと予想されます。結果として、短期滞在用の賃貸やホテル需要、さらには飲食・小売といった地域経済への波及効果が広がるのです。
2-7. アメニティ開発が生む“第二の価値波”
加えて、インターナショナルスクール周辺では、住宅だけでなく多様なアメニティが求められます。例えば、学習塾、語学学校、スポーツ施設、医療クリニック、カフェなどです。これらが充実すればするほど、地域の居住価値はさらに高まります。
特に、保護者のライフスタイルに直結する要素――コワーキングスペースや子ども同伴で利用できる飲食施設など――は、教育と生活をつなぐハブとして重要です。つまり、学校を核にしたエリア全体が「教育都市」として進化し、住宅需要を持続的に支える仕組みになるのです。
2-8. 賃料形成の実務
では、実際に教育需要が賃料にどのように影響するのでしょうか。答えは明確です。**「通学距離」「生活動線」「内装水準」**の3要素が掛け合わさって賃料が形成されます。
- 通学距離:徒歩圏、またはスクールバス路線上にあることが強力なアピールポイントとなる。
- 生活動線:朝の準備や学習に適した間取り、収納計画、採光設計が賃料プレミアムを生む。
- 内装水準:家具・家電・学習環境の充実度が再契約率を高める。
さらに、セキュリティやコミュニティの有無も保護者にとって重要です。つまり、単なる住まいではなく、教育に最適化された住環境が賃料を上振れさせるのです。
2-9. 価格安定のメカニズムを総括
以上をまとめると、インターナショナルスクールが住宅需要を押し上げるメカニズムは以下のように整理できます。
- 通学距離の近さが住宅の代替困難性を高める。
- 在学期間の長期性が居住需要を固定化する。
- 親世帯と投資家の需要が重なることで市場が二重に支えられる。
- 授業料割引などのインセンティブが購入を即決させる。
- 寄宿舎やアメニティ開発が需要の地理的範囲と多様性を拡張する。
このように複数の要素が組み合わさることで、教育近接住宅は「価格が上がりやすく、下がりにくい」という特徴を帯びるのです。
第3章:地方都市別の動向比較
3-1. バンコク ― 飽和市場と郊外シフト
タイの首都バンコクには、100校以上のインターナショナルスクールが集中しており、アジア全体でも有数の教育集積地となっています。バンコクの特徴は以下の3点に集約されます。
- 都市中心部の飽和:都心の土地価格は高騰し、新規開発余地は限定的。学校同士の競争も激化し、差別化のためにブランド校(英国・米国の名門系列)が積極的に進出。
- 郊外エリアへの拡張:バンナー、ラチャプルック、ラームイントラなど、通学アクセスが比較的良好な郊外で新規校や住宅開発が増加。ここでは住宅価格が都心より抑えられ、**“教育×郊外型ライフスタイル”**を求める層が集まる。
- 外国人駐在員の集積:大使館や国際企業が集中するため、英国・米国・日本・韓国など多国籍な駐在員家族が住む。特に日本人家庭にとっては、バンコク日本人学校とインターナショナルスクールの選択肢が並存し、多様な教育パスを形成している。
結果として、バンコクは「ブランド校志向+郊外シフト」という二重の構造変化を見せています。都心部での価格安定性は依然として高い一方、郊外では「教育を契機とした新興住宅地形成」が活発化しています。
3-2. チェンマイ ― 中国人需要の一大拠点
チェンマイは、タイ第2の都市として観光と教育の両面で発展してきました。現在、25校のインターナショナルスクールが存在し、バンコクに次ぐ規模です。
特筆すべきは、中国人家庭からの強い需要です。背景には以下の要素があります。
- 中国国内の教育規制強化:義務教育段階で外国カリキュラムが制限され、多くの家庭が海外に教育機会を求めている。
- コスト競争力:北京では年間100〜200万バーツに達する学費が、チェンマイでは40〜60万バーツに収まる。
- 生活環境の魅力:気候が温暖で、自然と都市機能がバランスよく共存。北京や上海に比べると生活コストが安く、長期滞在に適している。
そのため、チェンマイのインターナショナルスクールに通う約8,000人の生徒のうち、3,000人が中国人という構成に。これは「教育移住」という現象を顕在化させており、住宅市場でも中国人オーナーや借主の存在感が高まっています。
3-3. プーケット ― 観光リゾートと教育投資の融合
プーケットは観光地として有名ですが、同時に16校のインターナショナルスクールが存在し、外国人居住者の教育ニーズに応えています。
特徴的な動きとして、デベロッパーと学校の提携があります。例えば、SkyLuke Propertyは自社の高級ヴィラ購入者に対し、ルアムルディー・インターナショナルスクール・プーケットの授業料50%割引を提供。教育費優遇を直接的に住宅販売促進に結び付けています。
また、観光リゾートとしての魅力から、欧米やロシアからの移住者も多く、国籍の多様性が市場の安定性を高めています。さらに、ブリティッシュ・インターナショナルスクール・プーケットなどの有名校が集まることで、教育水準が国際的に認知され、住宅投資先としてのブランド力を押し上げています。
3-4. チョンブリ(パタヤ) ― EEC政策の追い風
タイ政府の東部経済回廊(EEC)政策による投資誘致の中心地であるチョンブリは、工業団地・物流・観光の三本柱で発展しています。これに伴い、外国人駐在員家族が急増。
ラグビー・スクール・タイランド(英国ブランドの寄宿学校)の進出や、サイアム・モーターグループによる新校計画など、教育需要が高級住宅需要をけん引。ここでは特に駐在員賃貸市場が強く、投資家にとって安定利回りが期待できる点が魅力です。
3-5. 地方都市比較のまとめ
- バンコク:競争激化・郊外拡張
- チェンマイ:中国人需要が突出
- プーケット:リゾート+教育投資の融合
- チョンブリ:EEC駐在員需要
それぞれの都市は異なるドライバーを持ちながらも、「インターナショナルスクールが住宅市場を牽引する」という点で共通しています。
第4章:デベロッパー戦略の進化
4-4-1. 教育主導型開発のシナジー効果
デベロッパーが学校と住宅開発を一体化することで、以下のシナジーが生まれます。
- 安定した顧客基盤:学校に通う子どもを持つ家庭は、必然的に近隣居住を選択。
- 資産価値の向上:教育環境が住宅価格を安定させ、転売・賃貸の両面で有利。
- 販売促進効果:授業料割引などの特典が、住宅購入を決定づけるトリガーになる。
- 国際的ブランド形成:学校と住宅をセットにした“教育コミュニティ”は、外国人投資家にも訴求。
4-2. インセンティブ戦略 ― 授業料割引の威力
実例として、あるデベロッパーは住宅購入者に対しインターナショナルスクール1年間授業料無料を提供。この場合、家族にとっては年間50万〜100万バーツの節約に相当し、住宅購入の意思決定に直結します。
さらに、SkyLuke Propertyが行ったような授業料半額キャンペーンも、富裕層家庭に強く響きます。教育費は毎年必ず発生する支出であるため、**「教育費が減る=生活コストが下がる」**という実感が即効性を持つのです。
4-3. リスク管理の視点
一方で、教育主導型開発には以下のリスクも存在します。
- 初期投資の大きさ:学校建設には数十億バーツ単位の資金が必要。
- 生徒確保の不確実性:出生率低下や他校との競争で入学者数が想定を下回る可能性。
- 規制リスク:外国カリキュラムへの制限など、政府の方針変更が影響を与える可能性。
- 人材確保の課題:優秀な外国人教師の確保は常に難題。ビザ・労働許可・待遇コストが重荷になり得る。
4-4. 長期的な価格安定のメカニズム
学校と住宅を組み合わせたモデルは、長期的に価格安定要因となります。
- 長期就学=長期居住の連鎖が続く限り、需要は途切れない。
- 投資家賃貸需要が市場を支え、空室率を低く保つ。
- 教育コミュニティの形成がブランド価値を高め、転売市場でもプラス評価を受ける。
4-5. 投資家への示唆
投資家にとってのポイントは以下の通りです。
- 教育近接物件は中長期保有で勝ちやすい
- 改装投資で賃料段差を狙う
- 学校の拡張計画(Year 13・寄宿舎)をKPIとして追跡
- 授業料優遇インセンティブを活用した売却戦略も有効
4-6. まとめ
デベロッパーにとって「教育主導型開発」は、住宅販売の一手段を超えて、新しい収益モデルとなりつつあります。学校と住宅が相互に需要を支え合う構造は、タイ不動産市場の次なる成長エンジンと位置付けられるでしょう。
第5章:マクロ経済と政策的背景
5-1. 外国人誘致政策との親和性
タイ政府は長期滞在ビザ(LTR)や投資優遇政策を通じて富裕層外国人を呼び込んでいます。教育インフラの充実は、移住決定における決定的要因であり、政府方針と完全に合致しています。
5-2. 地方都市への波及
2023年以降、バンコク以外のインターナショナルスクール数は急増し、2024年には地方がバンコクを逆転するとの予測も。都市開発・インフラ整備も同時進行し、地方都市の格差是正にも寄与。
第6章:将来展望 ― 教育ハブとしてのタイ
6-1. Year 13・寄宿舎拡張がもたらす新波及効果
- 生徒の在籍期間が延び、住宅需要はさらに長期化
- CLMV諸国や遠隔地からの留学生誘致が進む
- 地域経済への消費波及効果が拡大
6-2. 投資家への提言
- 中長期投資:インターナショナルスクール周辺物件は10年以上の長期スパンでの保有が有利
- 多様化戦略:住宅だけでなく、教育関連サービス(学習塾、カフェ、学生向けアパート)も高い潜在需要
- 国際比較:中国・シンガポールと比べた授業料競争力を武器に、外国人投資を積極的に呼び込むべき
結論:インターナショナルスクールはタイ不動産の「金鉱脈」
2025年の今、タイ不動産市場において最も注目すべきセクターは間違いなく 「インターナショナルスクールと連動した住宅市場」 です。教育需要が住宅価格を押し上げ、投資家に安定収益をもたらし、都市開発を促進するという三位一体の効果は、他の不動産セグメントでは類を見ません。
教育は子どもの未来を築くだけでなく、都市の未来、不動産市場の未来をも左右する力を持っています。タイは今、その実例を世界に示しているのです。


















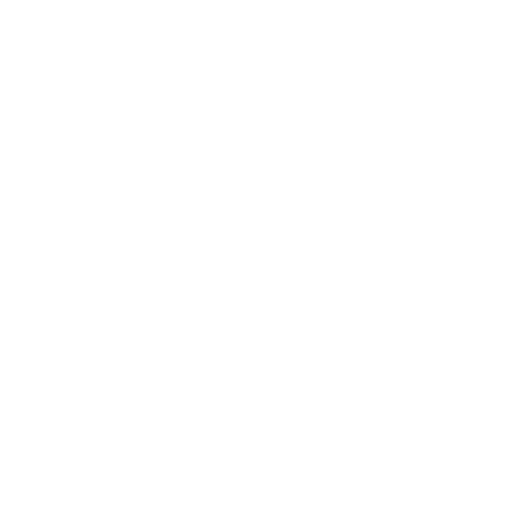

コメント