
8月22日付のBangkok Postは、「住宅市場は今月で底入れ、年後半は横ばい見通し」と報じました。過剰在庫と需要鈍化が続く中で、反発の芽はまだ小さい——これが足元のコンセンサスです。バンコクポスト
ただし本稿の焦点は、「底」であっても回復が早い“島”がどこに生まれるか。鍵を握るのが、バンコク首都圏で段階導入が進む20バーツ均一運賃制度です。政府は8月25日から「ทางรัฐ(Tang Rath)」アプリでの登録を開始し、10月1日から13路線(約280km)での本格適用を打ち出しています(対象はタイ国民の登録制)。一方で、関連法の成立状況次第では開始時期の遅延リスクも指摘されています。
本記事では、この制度を「都市設計のレバー」として捉え、①制度の要点、②市場への波及メカニズム、③早く回復しそうなエリアと商品類型、④投資家・デベロッパーの実務アクションを簡潔に整理します。
1) 制度の要点
- 目的:生活費の軽減と公共交通利用の促進。最低賃金の10%を超えない運賃水準を志向。渋滞・PM2.5の緩和や生活の質の改善も狙う。
- 適用範囲と時期:2023年10月にレッドラインとMRTパープルラインで試験導入。2025年9月30日までに全13路線(総延長約280km・194駅)へ拡大予定(BTSグリーン/ゴールド、MRTブルー/イエロー/ピンク、SRTレッド、ARL等)。試験導入後、~2024年6月で乗客数+26%。
- 利用条件:タイ国民限定で「ทางรัฐ(タンラット)」アプリ登録(予定:2025年8月25日開始)。決済はEMV非接触カードまたは登録済みRabbitカード。
- 財源と論点:初年度約700~800億バーツの補助想定。2年目以降は基金運営を想定。PPP(Net Cost)の下では**「乗車あたり補償」が現実解とされ、財政負担増が懸念。制度は恒久化の明確化と三法案**(共同チケット、タイ高架鉄道公社、鉄道運輸)の2025年8月30日までの可決が鍵。
重要な注記:**外国人(旅行者・長期滞在者含む)は制度対象外の見込み。**直接の恩恵は限定的ですが、タイ人通勤層の移動コストが下がることにより、賃貸・売買の需要地図は広がります。
2) いまの不動産市況と制度が生む“逆風下の追い風”
2025年のタイ住宅市場は、購買力の鈍化・過剰供給・厳格なローン審査で厳しい局面。一方で本制度は、**「通勤コストを恒常的に下げる」ことで、郊外選好と駅周辺の再配置(TOD)**を促し、在庫の吸収を後押しする“実需起点のテコ”として機能します。
3) 波及効果(5つの焦点)
① 郊外活性化と居住分散
- 通勤コストの劇的圧縮:従来は郊外⇄都心の往復で最大200バーツ+フィーダー費(バイク等)で月8,000バーツ超に達するケースも。均一20バーツで広く軽減し、**「都心の狭小」→「郊外の広さ」**への選好転換が進む。
- 注目エリア:ラマ9、バンワー、オンヌット、ベーリング、ミンブリー。駅から3~4km圏の物件にも波及。
- 価格帯と商品:300~500万バーツの中間層向け(コンド・戸建・タウンハウス等)が主役に。
② 既存路線の需給修正
- MRTパープルライン:最大の受益候補。運賃高が普及阻害だったが、均一運賃で吸収率改善が期待。ノンタブリ県の売れ残り(コンド200~300万バーツ帯、戸建300~500万バーツ帯)の解消に寄与の余地。
- SRTレッドライン:活性化見込み。ただし沿線地の多くが国鉄所有で、既存交通利便や車移動主体の高所得層が厚いエリアは新規開発の加速度合いは限定的か。とはいえ戸建約1,600戸・コンド約1,200戸の在庫調整にはプラス。
③ TOD(公共交通指向型開発)の後押し
- 運賃引下げは駅をハブとする複合開発(住宅・商業・公共空間)を促進。一極集中の緩和とローカル経済圏の形成に追い風。
④ 市場心理と販売戦略
- **利用者増(+26%)**という“行動変容の予兆”が確認済み。販促は「通勤時間×費用の可視化」「乗換コストの心理的抵抗の低下」を訴求軸に。
⑤ 中長期の価格形成
- 郊外土地の底上げ+駅半径のプレミア再評価。ただし制度の恒久性が明確にならない限り、価格の一方向的上昇は描きにくい。
4) エリア短評 & 駅距離の“勝ち筋”
- ラマ9:都心接続の良さとオフィス需要の近接で分譲・賃貸とも機動的。
- オンヌット/ベーリング:既に日本人にも馴染みある生活利便+価格優位。賃貸需要の下支え厚い。
- バンワー:河西側の結節。周辺再開発・乗換利便を取り込みたい。
- ミンブリー:東側アクセスの“遠さ”の心理障壁が低下。新規供給の目利きが要。
- 駅から3~4km:フィーダー導線(バイク・バス)と生活利便(市場・病院・学校)のセット評価で“駅前過密”を回避したCP重視の選択肢に。
5) プレイヤー別アクションプラン
投資家(個人・機関)
- 「家賃<通勤費節約」検証:ターゲット層の月間通勤節約額を見積もり、家賃(or返済)に転化できる上限を逆算。
- 在庫厚い区画の“良い在庫”探索:パープル/レッド沿線の管理・共用部レベル、駅距離×フィーダー、周辺生活利便でふるい。
- 出口戦略:賃貸はタイ人通勤層中心にプロダクト設計(家具・Wi-Fi・家電の初期負担軽減)。売却は**制度恒久化の里程標(法案可決・基金設計)**のアナウンス期を意識。
- 外国人は直接恩恵外:自らの運賃は下がらない点を踏まえ、“タイ人テナント需要増”に着目。
デベロッパー
- 価格帯の最適化:300~500万バーツの在庫回転を最優先。駅半径×フィーダー導線を販売資料に明示。
- TOD文脈のMD:駅直結でなくても**“乗換・待ち時間短縮”**を体験設計(動線掲示、モビリティ連携)。
- パープル沿線の在庫消化策:家具・家電パッケージや低初期費用プランで“賃貸→購入”の導線を。
6) リスクと不確実性(必ず確認)
- 制度の持続可能性:補償スキーム(収入減少補償/乗車あたり補償)と財源の安定性が未確定。
- 法制化の行方:共同チケット等の三法案が2025/8/30までに可決見込みとはいえ、遅延・修正リスクは織り込みたい。
- 政策の一時性リスク:恒久化が明文化されない限り、価格や賃料の期待先行→反動に注意。
- 需要の偏在:一部人気駅・区画への集中による賃料・地価の過熱と、その反動に要警戒。
- 金融環境:厳格なローン審査の継続により、販売→引渡しまでの落ち率(キャンセル)管理が重要。
7) まとめ:逆風相場の“構造テコ”
- 運賃20バーツは、通勤の定常コストを下げる=住まいの地理的選択肢を広げる政策。
- 郊外の中間価格帯(300~500万バーツ)とパープル/一部レッドの在庫吸収に実需の追い風。
- TODの促進で駅半径の価値再配分が進む一方、制度恒久化×財源設計が未確定のままでは価格形成の上値は限定。
- 実務は「制度の里程標(登録開始・法案・基金設計)」をトリガーに、在庫の良し悪し選別と通勤節約価値の可視化で一歩先に動くのが肝要です。

















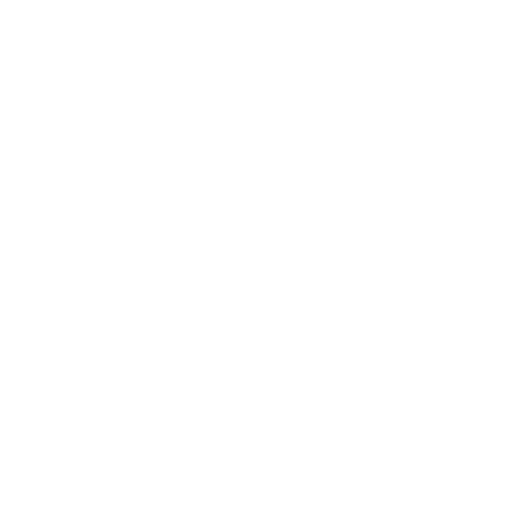

コメント